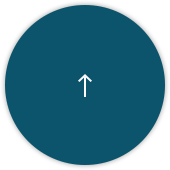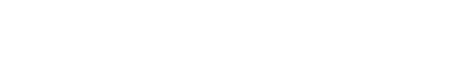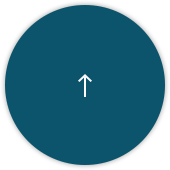大阪芸術大学 卒業制作展2025出展商品の共同開発者 片山夏実さんへのインタビュー - MIRAI BAR(ミライバー)株式会社|IoT・空中ディスプレイをもっと身近に、便利に
ニュース
- ホーム>
- ニュース>
- 大阪芸術大学 卒業制作展2025出展商品の共同開発者 片山夏実さんへのインタビュー
大阪芸術大学 卒業制作展2025出展商品の共同開発者 片山夏実さんへのインタビュー
1月7日付ニュースリリース「大阪芸術大学 卒業制作展2025にて共同開発商品が受賞作品に活用!」の受賞作品作者にインタビューしましたのでお知らせいたします。
片山夏実さんインタビュー
大阪芸術大学 芸術学部 デザイン学科 デジタルアーツコース
作品名:「遊界:ネクサス」
作者 片山夏実さんコメント:
「遊界:ネクサス」は、現実と仮想の境界線を繋げて遊ぶインタラクティブデジタルアート作品です。2体の3Dキャラクターが、人とのふれあいに合わせて魅力的に反応し、没入感のある体験を生み出します。空中ディスプレイやゲーム的要素を織り交ぜ、イラストを忠実に再現した立体モデルは、どの角度から見ても「かわいい」造形にこだわりました。デジタルとアナログ、平面と立体の垣根を越えて、誰もが楽しめる未来のエンタメ体験を提案します。
「遊界:ネクサス」

インタビュー 2025年2月20日(木)天王寺MIO11F
聞き手:MIRAIBAR(株)マーケティングシニアマネージャー 信濃義朗
片山さんはキャラクター達と共にそのキャリアを歩み始めた。「空中ディスプレイで操作が出来る事で、キャラクターの存在を、より親しいものに高められる。」
信濃:卒業作品が学科賞にえらばれて、ハルカスでの選抜展での展示になった事、まずはおめでとうございます。今日は、卒業作品の制作に携わられた感想や、今後の期待などお話を聞きたく思います。片山さんは、今、大阪芸術大学4回生ですが、芸大進学、コース選択の志望や動機を聞かせてください。
片山:もともと理系志望だったのですが、高校で少し不調な時期のあと、体調が戻った時に、社会的に有意義な事をというよりは、好きな事をやったらという感じに周囲がなってくれて、それなら、もともと芸術畑好きで、お休みしてる間にモデリングや3Dも触っていたので、それを学んでみようかと思い、自宅の近所だった事もあって、伊丹市にある大阪芸大の短大へ入学したのが22歳です。それから2年後、さらに意欲が湧いて、4大編入の道があったので本学にという経緯です。。
伊丹からは、ドアツードアで2時間くらいかかるので、大学の近くの喜志で一人暮らしさせて貰ってます。最近は、家族、母親にヘルプしてもらっていて、頻繁に来てもらっていて「半一人暮らし」みたいなものです。
短大でも、アニメやゲームのサブカルっぽい3Dへの興味から、「アニメーションデジタルコース」でしたが、4大編入時には、その延長線上で行けるコースが複数ありました。その中で、「キャラクタ造形学科」と「デザイン学科」で悩んで、自分がやりたい事が近かったので「デザイン学科デジタルアーツ」を選びました。
信濃:ティキィ小林先生のゼミに属してどうでしたか?
片山:ティキィ先生は、もとゲーム会社におられて、3年で3Dモデルの授業はあったのですが、どちらかといえば、技術を学ぶというより、クリエイティブへの心構えや、周りの環境をどう整えるかを学ばせてもらいました。
特に、友人関係ではみんなより良いものを創るというモチベーションが高くて、とても良い環境でした。行ってよかったです。
信濃:卒業制作として今回の作品に取組むきっかけを教えてください。
片山:流れが二つあります。今回の2体のキャラクターは、ずっと思い入れのあるキャラクタで、短大でも卒業制作に使ったんですが、その時は出来る事を詰め込みすぎて、「技術は色々使ってるけど、作品としてはちぐはぐ」になってしまったんです。不完全燃焼でした。今の私なら、そのキャラでどんな作品が作れるだろうかというのが一つの流れです。そして3年の時に空中ディスプレイのDEMOを見て、キャラクターと組み合わせて使ってみたいと思ったのがもう一つの流れですね。
このキャラクターは、短大に入学する時、自己紹介用の作品として自主的に見せた時から使ってます。困ったときは、出てきてもらう分身みたいなものです。自分が描きやすい絵柄や服装など、その時々の違いはあっても、同じキャラだと認識してます。
信濃:技術的には苦労しましたか?
片山:もともと短大の時に身に着けたモデリングの技術に加えて、UNITYで会話の出来る3Dモデリングといった、プラスアルファの技術を追加できた事で、コンテンツとして成立する作品に出来たのが楽しかったです。もともと、コンセプトとか作品の存在意義を定義するのが苦手で、創造的なクリエイターというより技術職に近いと思っていて、こつこつ繰り込むのが好きなのんです。友達に、作品の意図を明確に持ってる子がいますが、それは自分には足りない部分だなと。
信濃:そういう人とチームになるのはいいかも知れませんね。
片山:そうです。一人でやるのはしんどいんです。こだわりのある人を技術面でサポートするのが得意で、コンセプトや全部の意味付けから一人でやるのは苦手です。卒業制作の終盤で、他のゼミの先生にも聞いて回ったりして、コンセプトをなんとか後付けで整理しました(冒頭の本人コメント参照)。
短大の時も、モデリングや絵の技術は、ある程度あると思っていて、ハルカス展示のひとつ手前の賞を貰いましたが、ただ、自分だけで作るとコンセプトに欠けていて、技術的に出来るから作ったっていう感じでした。
空中ディスプレイを有効に活用が出来たか、インタラクティブをお客様に楽しんでもらえたかと言うと、もっとモーションの間隔とかタイミングとか、空中で触れるという事を、もっと効果的に演出できたし、まだ追及できたのではないかと思います。
今回、私が選ばれたのは、機材が目新しく、また、先生がたがデジタルアーツコースとして、「こんな事をしてます」と言いやすかったのかなと思っています。ものすごく優れたコンセプト持った友人の作品は映像系でクオリティも凄くて、まとまりも私より断然上だったんですが、なぜか私がコース賞に選ばれてとても驚いてしまいました。機材に下駄をはかせてもらいました。ありがとうございます。
■デザイン学科には1学年300人くらいの在籍者がおり、全7コースにわかれて在席している。各コース賞がコースごとに数名、さらにその上の学科賞は各コース1名の計7人が選ばれます。片山さんが取った学科賞の上には、さらに学科で一人の学長賞があります。片山さんの作品はデジタルアーツコースの作品として、想像力や表現力、技術面でたいへん優れているとされ、3名のコース賞のうちの1名に選ばれました。
信濃:デジタルアーツコースの作品展示を見たのですが、みなそれぞれアプローチが特有で、ものすごく多様だった。その中から、選ばれるってどんな感じですか。
片山:もちろん凄いうれしい気持ちもあるんですけど、まだまだブラッシュアップできる。モーションの創作も、期限にも追われてぎりぎり許せるといったレベルでした。空中ディスプレイ上のキャラクタが、頭を触られた時には、うまく反応をかえせたんだけど、身体を触られた時には、「一緒の遊びをする」という展開になっていたのですが、その反応が遅れたため、身体を触っても何も反応しないと取られてしまう事がありました。「遊ぶ」というスイッチは、その為のボタンを作ってその動きに移行させるべきだったのかも知れません。「頭を触ったら頭を触られた動作が起きたけど、身体を触ったのに、直接関係ない内容をしゃべりだした。」と感じられたのかも。
もうひとつ、UNITYでシステムを組む際に、1アプローチに対して起きるモーション=セリフが終了するまで、次のアプローチへの反応を切るという仕様にしました。これは、同じセリフを連打するのが嫌だなと思ったのですが、それが、触っても反応が起きないと取られました。その繋がりがわかりにくかったのが、一番大きな改善すべき点だなと。
信濃:空中ディスプレイって、操作したことを触覚としてわからないので、指先に触覚を与えるという事は技術的にはできても、商品として実現できていません。空間での操作を、操作者がどう受け取るかって事は、とても重要な話だと感じますね。
片山:触れているかわからないという問題は、スマホゲームでもあるように「タップエフェクト」が出る事で触ったことをわからせる事はやっています。改善点では、お客さんとキャラクタが「会話する」イメージを持たず、セリフの間を厳密に考えずに、キャラクタだけの間で声優さんに演じてもらったが事が、遊ぶモーションの時に、操作者に伝わらないまま、遊びが始まってしまうというようなコミュニケーションロストが起きた原因だと思います。キャラクタが「何をしようかな」と考える時間が長くて、お客さんを待たせたあげく、唐突にあっち向いてホイを始めるといったような事ですね。
キャラクタが一人で悩む時間があるなら、「触られた」→「何々?」→「遊びたいの?」→「それじゃ何しようか?」→「あっち向いてホイしよう」という流れが必要だったなと。
信濃: 今後、こんな機能が追加されたら面白いよねって期待はありますか?
片山:キャラクタに興味が寄っているので、そっち系の話しになりますが、ファンミーティング等で、自分の好きなキャラクタに空間で触れて、その反応があるというのは大変強いなと思いました。お客様からも言われましたが、普通のディスプレイとは違います。キャラクタに存在感が産まれます。そもそもキャラクタが空間に浮いていて、それが反応する、こちらに語りかけて来るという事だけでも面白いですが、それに触れるという事を有効に活かしていけるといいですよね。
信濃:ビジネス社会では、対面型のアバターやデジタルヒューマンといった技術で接客ができるといった時代になってきています。ただ、それでも違和感が残ってるのはどうしてかなと思っていましたが、問いかけた後の間が気になってるのかも知れませんね。人間だと、相手の質問に対して、何らかの反応=今考えますよというリアクションを挟みますが、それが抜けてるんだなと気づきました。
片山:そうそう。セリフだけでも、「ああなるほど、ちょっと待ってくださいね。」って挟むだけでも違うのかも。人間って何か聞かれた時に、ただぼーとしてなくて、表情が少しでも変わったり、ため息でもなんでも反応すると、聞いた側が自分が聞いたことが相手に伝わっている事が認知できるって事なんだなと思います。
信濃:クリエイターとして、こんなツールやサービスサポートがあるといいなとかってありますか?
片山:やっぱり入力を受ける機能をどう活かすかという事を有効に出来るといいですね。
そういった意味からは、手元キャラから吹き出しが出ていて、その吹き出しにタップすると、それに応じた動作が産まれるといった、よりキャラクタとの会話的なやり方が面白かったかもですね。「何々しましょうか?」という吹き出しにタップするとその動きが出るってのも面白いかも知れません。
信濃:今後は、創作においてどんな展開に興味がありますか?
片山:もともと、キャラクタが好きだったので、自分の作品は、ライブ2D等のイラストのモーション化、Vチューバ―のアバター化等の流れに沿ってるのではと思ってます。イラストが自在に動く事の楽しさ優先かも知れません。
信濃:そこに、なにか新しい文化が出てきている感じがしますよね。
片山:ライブ3Dだとどうなるかなと思いますね。展示していても、人数が多いと傍から見ていてもわからないので、立ち位置の誘導もあった方がよかったですね。
友達の影響が大きいんですけど、その友達に、「僕なら、機材だけの力に頼るのではなく、その機材で出来る事をいかに延ばすか、自分にしかできない事をいかに表現するかを考える」と言われました。アーティストだけど、マネジメントを考える子なんです。
信濃:社会に提案する新しい技術が、ちゃんと社会実装されていかない理由は、その技術をどう使えば、もっと有効で面白いものになるかというクリエイティビティが僕たちに欠けている事もあるのかも知れないですね。そういうものを芸術家の人たちと、開発側の人間が手を携えて新しいものを産み出していけるかもしれない事に希望が持てました。
本日は、とても貴重なお話を聞けて楽しかったです。就職先も決まったとの事。今後の活躍を期待しています。